「あ、ぬか床を混ぜ忘れてた!」
「キュウリを取り出し忘れて、いつの間にかしょっぱい古漬けになってた…」
ぬか漬け作りをしていると、誰もが一度は経験する、そんな「ぬか漬けあるある」ではありませんか?
しょっぱすぎて食べられない…と諦めてしまうのはもったいない!実は、そんな古漬けきゅうりを簡単に、ご飯がすすむ一品にリメイクするレシピがあるんです。
それが、昔ながらの知恵が詰まった「覚弥(かくや)」。
ほどよい酸味とうま味がたまらない、どこか懐かしい味わいは、一度食べたらきっとやみつきに。ぬか漬けの古漬け問題を救済し、食卓を豊かにするきゅうりの覚弥の作り方を、ぜひお試しください。
「ぬかから簡単に作るぬか床」も合わせてどうぞ


作り方をショート動画でチェック
- 0:03〜0:15:ぬか床から取り出した古漬けきゅうり(混ぜ忘れの失敗談も)
- 0:16〜0:22:しょっぱい古漬けきゅうりを薄切りにしてしっかり塩抜き
- 0:23〜0:32:すりおろし生姜、削り節、味の素で和える味付け工程
古漬けきゅうりレシピ「覚弥」
材料/分量:作りやすい分量
調理時間の目安:10分
- 古漬けのきゅうり 1本(100g)
- 水 500ml
- 生姜 少量
- 削り節 3g
- うま味調味料「味の素®︎」 3ふり
詳しい作り方
お漬物を切って塩抜きする
- ぬか床からぬか漬け(きゅうり)を取り出し、薄切りにする。
- 水に5分ほどさらし、しっかりと水気を絞る。



味付けする
- ボウルに①のきゅうりを入れ、生姜をすりおろす。
- 削り節と「味の素®︎」を加え、さっと和える。



おいしく作るためのコツやポイント
塩抜きは「味見」が最重要
古漬けの塩分濃度は、漬けていた期間や環境によって大きく異なります。5分というのはあくまで目安。きゅうりを水にさらした後、必ず一口味見をして、好みの塩加減になっているか確認しましょう。しょっぱすぎず、しかしきゅうりのうま味が抜けない絶妙な加減を見つけることが、美味しい覚弥への第一歩です。水気をしっかり絞ることも、味がぼやけないための大切なポイントですよ。
減塩とうま味の相乗効果を最大限に
一般的に覚弥には醤油を使うことが多いですが、このレシピではうま味調味料「味の素®︎」と削り節を使うことで、大幅な減塩を実現しています。
醤油小さじ1弱(3g)の食塩相当量が0.54gであるのに対し、「味の素®︎」3ふり(0.3g)の食塩相当量はわずか0.09g。これにより、約83%もの減塩が可能です。
さらに特筆すべきは、味の相乗効果です。削り節に含まれるうま味成分「イノシン酸」と、「味の素®︎」のうま味成分「グルタミン酸」を組み合わせることで、それぞれ単独で使うよりも何倍も強くうま味を感じられます。
これは「うま味の相乗効果」と呼ばれる科学的な現象で、出汁の美味しさの秘密にも通じるものです。少ない塩分でも満足感のある深い味わいになるので、ぜひこの組み合わせをお試しください。
薬味と和えるタイミング
生姜の爽やかな香りは、古漬けの独特の風味を和らげ、食欲をそそります。お好みで、みょうがや大葉、ごまなどを加えても、さらに香りと食感のアクセントが加わり、美味しくいただけます。
また、和えるのは食べる直前がおすすめです。時間が経つと、きゅうりから水分が出てしまったり、風味が飛んでしまったりすることがあります。作りたてのシャキシャキとした食感と、薬味のフレッシュな香りを楽しむためにも、ぜひ食べる直前に和えてください。

このレシピで摂取できる栄養
この「覚弥(かくや)」は、美味しくてご飯が進むだけでなく、私たちの体に嬉しい栄養素も含まれています
- きゅうり: 約95%が水分ですが、カリウムも豊富に含まれています。カリウムは体内の余分なナトリウム(塩分)を排出するのを助け、むくみの改善や高血圧予防に役立ちます。また、わずかながら食物繊維も含まれており、腸内環境のサポートにもつながります。
- ぬか漬け(発酵食品): ぬか漬けになる過程で乳酸菌が増殖します。これらの乳酸菌は、腸内環境を整える「腸活」に貢献し、免疫力の向上にもつながると言われています。また、ビタミンB群(B1, B2, B6など)も増えるため、疲労回復や代謝促進も期待できます。
- 生姜: 辛味成分であるジンゲロールやショウガオールが豊富で、体を温め、血行を促進する効果が期待できます。冷え性の方や風邪のひきはじめにも良いとされています。
- 削り節: 良質なタンパク質源であり、イノシン酸といううま味成分の宝庫です。タンパク質は筋肉や皮膚、髪の毛など体のあらゆる細胞の材料になります。
このレシピにおけるQ&A
他の、ぬか漬けのレシピ一覧はこちらから


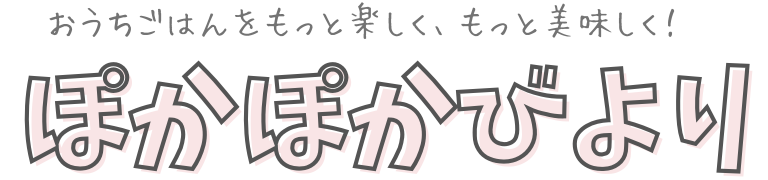

質問・感想など、ぜひ聞かせてください↓