大葉、ついつい買いすぎて余らせていませんか?
今回は、大葉をたっぷり消費できる、簡単なのに絶品の「大葉ちくわ串カツ」をご紹介します。
お手頃価格のちくわと大葉を組み合わせたこのレシピは、少ない油でサクサクに仕上がり、子供から大人まで大人気!揚げ物だけど時短でできて、晩ごはんのメインおかずはもちろん、お弁当にもぴったり。ぜひ、レパートリーに加えてみてくださいね。

こちら、古い方のブログでは2021年11月に。
インスタグラムでも、何回も紹介してきて、作ったよの声をたくさんいただいている大好評レシピです。
目次
レシピ 大葉ちくわ串カツ
材料:作りやすい分量(串5本)
- ちくわ:1袋(4本)
- 大葉:16枚
- パン粉:適量
- 揚げ油:適量
【A】バッター液
- 卵Mサイズ:1個
- 片栗粉:大さじ1
- 薄力粉:大さじ1
- 水:大さじ1
作り方
STEP
材料の下ごしらえ
- ちくわは1本を4等分ほどの筒切りにする。
- 大葉は軸を取り除き、半分に折り曲げ、切ったちくわを巻く。
- 大葉の巻き終わりが外れないよう気をつけながら、1本の竹串に3〜4個さす。

STEP
揚げる
- 【A】の材料を混ぜ合わせてバッター液を作る。
- 串に刺したちくわ大葉をバッター液にくぐらせ、パン粉を全体にしっかりつける。
- 170℃に熱した揚げ油で、衣が色づきカリッとするまでさっと揚げる。揚げすぎるとちくわが固くなるので注意する。

おいしく作るためのコツやポイント
- 衣の厚さで食感をコントロール
衣を全体にぎっしりつけると、サクサク感と食べ応えが増します。ちくわと大葉の風味をより楽しみたい場合は、衣を薄めに、またはちくわが見える程度に軽めにつけるのがおすすめです。 - 揚げ時間は「衣の色」を目安に
ちくわも大葉も生で食べられる食材なので、火を通すというよりは「衣をカリッと色づかせる」ことが目的。170℃の中温で、きつね色になったらすぐに引き上げてください。揚げすぎるとちくわが固くなり、食感が損なわれるので注意が必要です。(180℃〜190℃だと、大葉の色が悪くなるので、170℃にしています) - 少量油でOK!揚げ焼きでも美味しく
フライパンに底から1cm程度の少なめの油でも、揚げ焼きのように調理できます。これなら油の処理も簡単で、後片付けも楽になります。 - 大葉の巻き方と串の刺し方
大葉はちくわの筒に沿うように巻くと、揚げた時に剥がれにくいです。串に刺す際は、大葉の巻き終わりを串で固定するように刺すと、さらに剥がれにくく、見た目もきれいに仕上がります。

このレシピで摂取できる栄養
この大葉ちくわ串カツは、美味しさだけでなく、手軽に栄養も摂れる一品です。
- ちくわ: 魚のすり身が原料で、体を構成する良質なタンパク質が豊富。骨や歯を丈夫にするカルシウムも摂取できます。
- 大葉: 緑黄色野菜の代表で、粘膜や皮膚の健康を保つβ-カロテン(ビタミンA)や、免疫力アップを助けるビタミンCが豊富。体内の余分な塩分を排出するカリウムや食物繊維も含まれています。
揚げ物ではあるものの、工夫次第で油の量を抑えられ、バランスの取れた食事が実現します。手軽に作れて、元気な体づくりをサポートする一品です!
このレシピによくあるQ&A
写真付き!大葉を長持ちさせるコツ
大葉を長持ちさせるには、乾燥させない+適度な水分が必要です。
保存の適温は8℃前後と言われているので、冷蔵庫よりも野菜ボックスがおすすめです。
- 買ってきた大葉をそろえ、軸の切り口を1mmカットする
- 水を1cm弱入れて、軸だけを浸す


保存袋や買ってきた大葉の袋の場合は、袋を斜めにし水を端にため、野菜ボックスの側面にテープで貼り付けてもOK。カップを使う場合は、右の写真の状態にして上から袋をかぶせてください。
ブログ内の大葉レシピは、こちらにまとめています。
主菜から副菜、主食もあるので、ぜひご覧くださいね
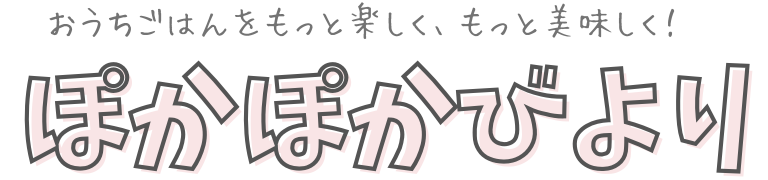

質問・感想など、ぜひ聞かせてください↓