今まで、もやしを使った料理はたくさん作りましたが、その中で家族に1番人気だったのが、この 砂肝もやしのポン酢炒め でした。
- もやしがたっぷり食べられる
- 少しとろみをつけて味をしっかり感じられる
- 砂肝の食感でボリュームUP
味付けは、ポン酢醤油&砂糖なので、ほんのり甘酸っぱくて、万人受けしますよ。
この記事の後半部分は、新鮮なもやしの選び方や保存方法についてまとめているので、そちらもよろしければご覧ください。

【砂肝もやしのポン酢炒め】の材料
材料:2人分
調理時間の目安:約10分
- もやし 1袋
- 青ねぎ(もしくはニラ) 1/3袋
- 砂肝 200g
- 塩 小さじ1/3
- 薄力粉 小さじ2
- 【A】砂糖 小さじ1
- 【A】ぽん酢醤油 大さじ1強
- 油 少量
1人分の
エネルギー:186kcal
食塩相当量:1.65g
栄養価は多い順に、ビタミンB12、ビタミンK、葉酸、鉄分
ほぼ含まれないものは、ビタミンD、ビタミンA、カルシウム
詳しい作り方
砂肝を焼き、もやしと粉を加える
- 砂肝に塩をしっかり揉み込み、下味をつける。
- フライパンに油をひき弱中火で熱し、砂肝を並べる。
- ふたをし、時々返しながら5〜6分蒸し焼きにする。
- 火を中火に上げ、もやしと薄力粉を加えて炒める。

仕上げの調味をする
- 粉っぽさがなくなったら、青ねぎを食べやすい長さに切りながら加える。
- 【A】の調味料をすべて回し入れ、全体に味が馴染むよう手早く混ぜ合わせる。
- 器に盛り付け、お好みで七味唐辛子を散らす。

コツ・ポイント
いつもの炒め物が、この3つのポイントを意識するだけで、お店のようなワンランク上の仕上がりになります
1. 砂肝の「銀皮」を制する者が、食感を制する!
砂肝の美味しさを左右するのが、青白く硬い「銀皮(ぎんぴ)」と呼ばれる部分の処理です。

- 基本は「削ぎ取る」:
この銀皮は加熱しても硬く、口に残りやすいため、包丁で丁寧に削ぎ取るのがおすすめです。このひと手間で、コリコリと歯切れの良い、理想的な食感に仕上がります。 - もったいない派は「切り込み」を:
もし捨てるのが惜しければ、銀皮の表面に包丁で格子状に細かく切り込みを入れてください。筋が断ち切られることで、食感が和らぎ、格段に食べやすくなります。
2. 「薄力粉」が味しみの最強サポーター
レシピにある「薄力粉」は、単にとろみをつけるためだけではありません。これが味の決め手となる重要な役割を果たします。米粉で代用しても構いません。
- 効果:
薄力粉が食材の表面を薄くコーティングすることで、ポン酢ベースのタレが驚くほどよく絡みます。味がぼやけず、最後の一口までしっかりとした味わいを楽しめます。タレが皿の底に溜まってしまう、という失敗も防げます。
3. 味付けは「お使いのポン酢」を基準に調整を!
ポン酢醤油はメーカーによって塩分、酸味、甘みのバランスが大きく異なります。
- 基本の考え方:
まずはレシピ通りの分量で試してみてください。その上で、味見をしてから微調整するのが成功の秘訣です。 - 調整の目安:
- 塩味が強いポン酢なら、分量を少し減らす。
- 酸味がキリッとしているポン酢なら、砂糖を少し足して角を取る。
- 甘みの強いポン酢(だしポン酢など)なら、砂糖を減らすか、無しにする。
ご家庭の味に合わせて「我が家の黄金バランス」を見つけてみてください。

このレシピの栄養まとめ
食感もよいですし、暑い夏でもさっぱりと食べられる「砂肝もやしのポン酢炒め」 栄養面についてまとめます。
- 摂取できる栄養素:
たんぱく質、鉄分、ビタミンB群、食物繊維、カリウム、ビタミンC(少量)、脂質などが摂れます。 - 含まれない栄養素: 主食となる炭水化物(エネルギー源)、カルシウム、多くの種類のビタミン(特にA、Dなど)やミネラルが不足しがちです。
バランスの取れた献立のために、一緒に合わせるとおすすめのメニューを3つ提案します。
- ごはん(白米、雑穀米、玄米など):
エネルギー源となる炭水化物をしっかり補給できます。 - 具だくさん味噌汁(豆腐、わかめ、きのこなど):
植物性たんぱく質、カルシウム、食物繊維、その他ミネラルを手軽に摂ることができます。 - ほうれん草のおひたし(またはその他の緑黄色野菜のおかず): ビタミンA(β-カロテン)、ビタミンC、鉄分、食物繊維などを補給し、彩りも豊かになります。



もやしについての豆知識
【スーパーで失敗しない】新鮮もやしの見分け方
美味しいもやし料理を作る第一歩は、新鮮なもやしを選ぶこと。この3つのポイントをチェックしてみてください。
- 【見た目】豆がしっかり、全体が白くツヤがある
ひげ根が茶色く変色していたり、袋の中に水が溜まっているものは鮮度が落ちているサインです。 - 【食感】袋の上から触れて、パリッとしている
しんなりしているものより、触れただけでポキッと折れそうなほど、ハリのあるものを選びましょう。 - 【臭い】特有の青臭さがない
酸っぱいような臭いがするものは傷み始めている可能性があるので避けてください。
もやしは【袋のまま】が正解!鮮度を保つシンプル保存術
もやしは足が早いのが悩みどころ。色々な保存法がありますが、私が色々試して行き着いた、一番手軽で栄養も逃しにくい方法をご紹介します。
冷蔵保存(2〜3日以内に使うなら)
- 結論:袋のまま、チルド室か野菜室へ
- 理由: 購入時の袋は、もやしに最適な環境に調整されていることが多く、そのまま保存するのが一番鮮度を保てます。
- ポイント: 袋の口を少し開けておくか、爪楊枝で数カ所穴を開けておくと、もやしが呼吸して出すガスが抜け、さらに長持ちしやすくなります。
冷凍保存(約1ヶ月ストックしたいなら)
- 結論:買ってきた袋のまま、何もせず冷凍庫へ
- 理由: 水洗いや下茹でをせず生のまま冷凍することで、解凍時の水っぽさや食感の劣化を最小限に抑えられます。
- 使い方: 凍ったまま、炒め物やスープ、味噌汁に直接投入してください。
よく「水に浸して保存するとシャキシャキ感が長持ちする」と言われますが、この方法だとビタミンCなどの水溶性の栄養素が水に流れ出てしまいます。栄養面を考えると、袋のまま保存するのがおすすめです。
【実は優秀】知っておきたい”もやし”の栄養パワー
「もやしは栄養がない」なんて思っていませんか?それは大きな誤解です。低カロリーなだけでなく、私たちの体に必要な栄養素がしっかり含まれています。
緑豆もやしに含まれる栄養は以下の通り
(栄養成分含有量については、100gあたりで表記されるので、もやし1袋=約200gに換算しています)
- 食物繊維:2.6g
→お腹の調子を整えるのに役立ちます。 - ビタミンC:16mg
→美容や健康維持に欠かせない栄養素。加熱で失われやすいので、炒め物など短時間で調理するのがおすすめです。 - カリウム:138mg
→余分な塩分を体の外に出す手助けをしてくれます。
低カロリーでかさ増しにもなるもやしは、ダイエットや節約の強い味方です。他の肉や野菜と組み合わせることで、栄養バランスもさらにアップする、とても優秀な食材なんですよ。
1日の必要量からパーセンテージを求めると… 食物繊維は13%。ビタミンCは16%(ただし調理方法にもよります)なので、他の食材とうまく組み合わせて調理しましょう。


もやしの人気レシピはこちらからご覧ください
このレシピは、味付けがしっかりしているので、ご飯がかなりすすみます!

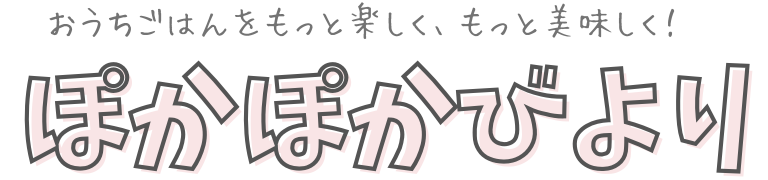

質問・感想など、ぜひ聞かせてください↓